安否確認システムとは、地震などの災害発生時に従業員の安否や被災状況を、迅速・的確に確認できるシステムです。本記事ではメリット、機能、タイプ別の選び方、比較ポイントなどをおすすめのサービスを交えてわかりやすく紹介します。
“安否確認システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)
安否確認システムとは、地震などの災害発生時、従業員の安否確認をスムーズに行い、事業継続性を担保するためのシステムです。
従来、災害などが発生した場合、担当者が個々の従業員に電話・メールやチャットなどで、「大丈夫ですか」「怪我はないですか」など手動で連絡するのが一般的でした。しかし、「担当者自身が被災して安否確認ができない恐れがある」「発信・集計に時間がかかる」「正確に全体状況を把握するのに手間がかかる」といった課題がありました。
安否確認システムを導入した場合、以下のような手順で安否確認が行われます。従来の電話・メールなど手動で行うのに比べて、効率的な運用が可能になります。
近年では、地震に限らず、台風やゲリラ豪雨、大雪などでも利用されており、従業員の安全確保はもちろん、BCP(事業継続計画)への対策の一環として整備する企業が増えています。
安否確認システムは、「何を重視するか」によって以下の図のように、3つのタイプに分けられます。

記事後半では、タイプごとにおすすめのサービスの詳細を紹介していますので、今すぐ確認したい方は以下の各リンクからご覧ください。
安否確認システムをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。
“安否確認システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)
安否確認システムを導入することによるメリットとしては、以下の5点が挙げられます。
1つずつ詳しく見ていきましょう。
安否確認システムの多くはメール・電話のほかに、アプリ・SNS・自動音声ガイダンスなど、複数の連絡手段に対応しています。また、同じメールでの連絡についても、大規模災害にありがちな遅延を減らしたり、サーバーがダウンせずに利用できたりと、到達率を高めるための様々な仕組みがとられています。
加えて、連絡先を従業員自身が入力・変更できるものなら、担当者のメンテナンスの手間が省けます。「情報が更新されていないせいで、いざという時に連絡がつかない」という心配もありません。
多くのシステムは気象庁の地震情報に連動して、実際に地震が起こったら、自動で安否確認メッセージを配信。従業員は「怪我の有無」「出社の可否」といった質問に対し、アンケート形式・プルダウン形式で回答できます。
更に、結果は自動で集計され、管理者は一覧や円グラフなどで状況を確認可能。「安否確認が取れていないのは誰か」「各部署・エリアどのような被害状況か」などを容易に把握できます。
また、「従業員が自分で連絡先の登録・更新ができる」「社内の人事データからユーザー情報を一括更新できる」など、普段のメンテナンス作業を効率化する機能も要チェックです。
災害発生後、企業担当者は「今後の体制」「業務の割り振り」などについて従業員に連絡をする必要があります。その際に安否確認システムを使えば、被災地エリアに居住する従業員だけに二次連絡をしたり、安否確認の集計データを利用して「明日出社が難しい従業員」をグルーピングして連絡したりと、細かな設定ができます。
中には、双方向で情報をやりとりできるメッセージ機能・掲示板機能などを備えたシステムも。
従業員本人が無事でも、家族が被害に遭っていれば出社や業務遂行は難しくなります。そのため、企業は従業員の家族の安否確認まで行う必要があります。
安否確認システムの中には、従業員同様に家族の連絡先を登録して、いざという時、家族に直接安否確認ができる便利なものも。家族安否確認機能は、登録した家族のみ閲覧できるため、家族の個人情報が会社に伝わる心配はありません。
家族安否確認機能は、登録した家族のみ閲覧できるため、家族の個人情報が会社に伝わる心配はありません。
非常時でも連絡がつきやすいよう、安否確認にはプライベートな電話番号・メールアドレスが使われることも。そのため「管理者や会社に申告したくない」と登録を拒む従業員がいて、安否確認がスムーズにいかない理由の一つになっていました。
その点、従業員自ら連絡先などの個人情報を入力するタイプの安否確認システムなら、プライベートの連絡先を管理者に知られる心配はありません。
セキュリティ対策のとられた事業者側のサーバーに保管されるため、情報漏えいのリスクが小さいのもメリットです。
安否確認システムの機能としては、以下のようなものが挙げられます。
| 一斉配信 | 従業員に自動で安否確認メッセージを一斉配信できる |
|---|---|
| 気象庁連動 | 事前設定した気象庁の情報に連動して自動配信できる |
| 自動再配信 | 安否確認に回答がない従業員には自動で再配信できる |
| 予約配信 | 予め日時を決めて送信できる。緊急時以外の平時利用に必要 |
| 限定配信 | 配信対象者をグループや役割等で区切って限定送信できる |
| 家族への対応 | 従業員が登録した家族にも同様に安否確認を行える |
| GPS取得 | 回答と同時に位置情報を取得できる。救助にも役立てられる |
| スマホアプリ | 専用のスマホアプリを用いて安否確認を行える |
| LINE利用 | LINEで安否確認を行える(個人LINEを利用できるものも) |
| 設問設定 | 設問を「怪我の有無」「出社などの可否」などカスタマイズできる |
|---|---|
| 自動集計 | 安否確認に対する回答を自動で集計できる |
| ダッシュボード | 集計結果をグラフなど可視化してわかりやすい状態で把握できる |
| 音声回答 | 音声通話でガイダンスにしたがって回答させることができる |
| 掲示板 | 掲示板を設置して、不特定の従業員同士が情報交換できる |
| 多言語対応 | 英語や中国語、ベトナム語など従業員に合わせて自動翻訳できる |
安否確認システムには、上記のように便利な機能が豊富に搭載されていますが、システムやプランによって対応の有無は異なります。主だった安否確認システムについて機能比較表を作成していますので、サービス選びの参考にしてください。
「もっと詳細を知りたい」「じっくり選びたい」という方は、以下の「安否確認システムの選び方ガイド」をダウンロードしてご利用ください。13システムの機能をより細かく比較しています。
安否確認システムの選び方ガイド(比較表付き)
安否確認システムは「何を重視するか」によって3つのタイプに分けられます。それぞれどういった機能があると便利なのか、どういったサービスが存在するのかを言及していきますので、サービス選びの参考にしてください。
災害発生時に、効率性もさることながら「システムが確実に動作するか」確動性を重視する場合です。安否確認システムをうたっているシステムでも、「負荷が集中しすぎて動作しない」「データセンターが被災して稼働できない」ということは起こりえます。緊急時の安定感を重視したい場合は、以下のポイントをチェックしておきましょう。
| 主なサービス名 | 特徴 | 実績 |
|---|---|---|
| Biz安否確認/一斉通報 | 東日本大震災での運用実績あり。異常気象時にも利用でき、階層別管理で柔軟な運用が可能。 | 2,300社 |
| 安否コール | 東日本大震災でも稼働。グッドデザイン賞受賞の使いやすいUXデザインも特徴。 | 1,300社 |
| 安否確認サービス2 | 安否確認に加え、メッセージ・掲示板機能で災害時やテレワーク時のコミュニケーションも可能。 | 4,000社 |
| エマージェンシーコール | 24時間365日監視体制で、関東と関西のデータセンターで同時稼働。大震災でも高い回答率を保持。 | 5,200社 |
| セコム安否確認サービス | 安否確認メールを代行送信も可能。送信手段はメール・専用アプリ・LINEに対応。 | 9,000社 |
| オクレンジャー | 日本初のスマホアプリの特許取得。受信登録IDに対する端末台数に制限なし。 | 4,000社 |
| ALSOK安否確認サービス | 国内の複数拠点にサーバーを設置し、災害時の稼働率を確保。 | 不明(2003年より提供実績あり) |
メールでの安否確認は「間違ったメールアドレスを登録する恐れがある」「迷惑メールにまぎれて確認できない」などの課題があります。日頃からメールをあまり利用しない企業の場合はなおさらです。この場合は、SNSやSMSで安否確認ができるシステムがおすすめ。以下のポイントをチェックしておきましょう。
| 主なサービス名 | 特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| ANPIC(アンピック) | スマホアプリに加えて、標準プランでLINEと連携して安否連絡が可能。 | 月額5,510円(100名まで) |
| 安否確認bot for LINE WORKS | 企業向けのLINE WORKSのほか、個人のLINEアカウントでも利用可能。 | 月額200円/名 |
| バンソウ緊急SMS | 携帯にデフォルトで搭載されるSMSを安否確認に利用。ガラケーの従業員にも対応可。 | 月額9,500円(31〜100名) |
安否確認システムは万一のリスクに備えた予算投下のため、できるだけコストを抑えたいという企業も少なくないでしょう。一般的な月額の目安は以下の通りです。
安否確認システムによっては、機能制限などはあるものの無料・安価に利用できるプランを展開しているものもあります。コストを重視する場合はそういったサービス・プランを検討するといいでしょう。ただし、コストを優先しすぎて、肝心なときに機能しなければ意味がありません。機能とコストのバランスは、慎重に議論・検討すべきポイントです。
| 主なサービス名 | 特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| ANPiS | 安価ながらも未回答者への自動再送信、LINE利用などの便利機能を搭載。組織階層も4階層まで対応。 | 月額9,000円(100名まで) |
| クロスゼロ | 利用人数が増えるごとにお得に。1,000名規模なら1人あたり月額20円。 | 月額12,000円(100名まで) |
| らくらく連絡網 | 700万人が利用する無料メーリングリスト。共通プラットフォームでやり取り可能。 | 無料 ※有料版は月額5,000円(100名まで) |
| e安否 | 20名までなら無料で利用可能。無料でもGPS機能を標準搭載。 | 無料(20名まで) |
安否確認システムの選定においては、目的別で絞り込んだうえで、更に以下のようなポイントに沿って比較検討していくとスムーズです。
ほとんどの安否確認システムは自動一斉配信機能を搭載しています。しかし、その配信方法は「①気象庁から取得したデータを自動配信する」「②ベンダーが災害データを精査してから配信する」「③災害データ受信後、数分たってから自動配信する」など、いくつかのパターンに分けられます。
たとえば、①は災害後の通信回線混雑や通信規制に巻き込まれにくく、②③は誤報を減らせるなど、それぞれにメリットとデメリットがあるため、それらを認識したうえでシステムを選ぶようにしてください。
また、組織構成が複雑な場合は「Biz安否確認/一斉通報」や「安否コール」のように、「どのエリア・所属・部署の従業員に送るのか」まで柔軟な設定ができるものを選ぶとより便利です。
より連絡をつきやすくしたいなら、一つの連絡手段にとらわれず、メール・アプリにSNS・SMS・自動音声ガイダンスなど、複数の連絡手段に対応しているものを検討しましょう。たとえば、「エマージェンシーコール」はアプリ・メールに加えて、音声応答・LINEなど多様な連絡手段に対応しています。
なお、前述した通り、従業員がメールを使い慣れていない場合は、最初からLINEやSMSなどで一斉連絡と回答収集を行うサービスがおすすめ。連絡手段は限られてしまいますが、LINEやSMSは基本メールよりも到達率・開封率が高いため効率的な安否確認が期待できます。
回答率や回答精度を上げるには、アプリ対応をしているシステムがおすすめです。アプリをインストールしておけばプッシュ通知が届くほか、メールアドレス不要で登録できる、回答時にログインが不要など、様々なメリットがあります。
しかし、アプリによっては「通知のみで回答ができない」「操作しようとするとブラウザに飛ぶ」など、操作性が異なります。たとえば「安否コール」はネイティブアプリを提供しているので、アプリ経由で回答ができるほか、スマートウォッチなどのIoT機器から回答することも可能。回答率の向上に役立ちます。
従業員が多い場合、一人ひとりにID・パスワードを発行して管理するのは大変です。「連絡先の変更」「パスワードの失念」などが起こるとなおさらです。その場合、従業員自身が空メールなどで登録作業して、自分で登録作業を行うタイプが便利です。
たとえば、「安否コール」はQRコードから新規登録可能。ID・パスワードも不要です。ログインする際も登録した電話番号にSMSを送って認証するだけなので従業員にとっても便利です。
災害時には従業員だけでなく、家族の安否確認も重要です。サービスによって標準対応しているものもあれば、有料オプションの場合もあるので、きちんとチェックしておきましょう。
たとえば、「安否確認サービス2」のファミリープランの場合、家族用に登録した最大8つのアドレスに安否確認を行うことができ、家族は限定の専用掲示板を利用してやりとりすることもできます。
外国籍の従業員がいる場合、多言語対応しているかできるかも重要なチェックポイントとなります。たとえば、「セコム安否確認サービス」なら、管理者用画面・従業員用画面を日本語と英語で切り替えて表示することができます。外資系企業や大使館などの導入実績も豊富なため、外国籍の従業員が多い企業にはおすすめです。
“安否確認システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)

(出所:Biz安否確認/一斉通報公式Webサイト)
東日本大震災でも運用実績を持ち、震度7・突発的な大量トラフィックにも耐えうる高信頼の安否確認サービス。あらかじめ設定した震度以上の地震が発生した際、自動で一斉メールやアプリで安否確認。そのほか、異常気象時の緊急連絡・指示にも利用可能。組織階層別に1〜10階層で管理者を設定して権限を割り振ることができるため、柔軟な運用ができる。
通常料金のほか、「月額10,000円・初期費用無料」と比較的安価で利用できるライトプランあり(1,000IDまで)。自動配信機能がないものの、スケジューリング機能や豊富なアンケートテンプレートを使えば、リモートワーク下の従業員の健康状態のチェックやトラブル時の現場状況の確認など平時にも利用可能。

(出所:安否コール公式Webサイト)
東日本大震災でも問題なく稼働した実績のある安否確認システム。社員100名未満の企業から数万名を超える大企業まで導入実績1,300社以上。企業規模に合わせた複数のプランがあり、すべてのプランで自動配信・家族安否機能を使用可能。国内外4カ所のデータセンター利用で安定稼働を図っている。
利用にはメールアドレス・パスワードは一切不要。スマホアプリからQRコードで認証を行うだけ。管理負担が少なく、グッドデザイン賞受賞の使いやすいUXデザインも特徴。安否確認のための機能はBCP対策だけでなく、ミーティングの案内・日時調整、社内イベントの出欠確認、健康診断・年末調整などの従業員連絡、お弁当を注文する際の希望者集計など普段使いも期待できる。中にはGPS機能付のデジタコの代替として活用している企業も。リモートワークにおける従業員の日々の検温でも利用されている。

(出所:安否確認サービス2公式Webサイト)
安否確認の一斉送信だけでなく、それに紐付いた多彩なコミュニケーション機能を持つ安否確認サービス。たとえば「大災害翌日に全社員を自宅待機にするのか・通常出社させるのか」などを主要メンバーで議論したり(メッセージ機能)、現在の状況や今後の予定を従業員と共有したり(掲示板機能)。掲示板にはマニュアルや写真も添付可能。災害時だけでなく、テレワーク下での従業員の健康管理(新型コロナウイルスの感染症対策)、社内外のインフラやシステム障害時の状況確認、職員旅行のアンケート集計など、普段使いもできる。
安否確認は地震だけでなく、津波や特別警報にも連動して自動通知。連絡手段はメール、パケット通信、専用アプリ、X(Twitter)。データセンターはシンガポールをメインに米国、日本を加えた3拠点。BCP対策としても安心。

(出所:エマージェンシーコール公式Webサイト)
安否回答率・連絡内容確認率100%達成を目標に掲げる安否確認サービス。導入実績5,200社以上。一人の従業員につき、メールアドレス・電話番号(固定・携帯)・アプリなど、最大10個まで連絡先を登録可能。回答またはメッセージ確認があるまで、最大100回まで繰り返し発信するため、通信状態が悪い場合でも安心。サービスの安定稼働に強みを持ち、24時間365日の監視体制で、関東と関西の2つのデータセンターで同時稼働。東日本大震災・熊本地震でも安定稼働と高い回答率を保持。
管理者の人数・組織階層に制限はなく「大量の社員情報をCSVで一括登録可能」「グループ企業を含めた運用設定」「様々なデバイスからの連絡発信」など、運用管理者の負担を軽減する工夫あり。

(出所:セコム安否確認サービス公式Webサイト)
契約社数9,000社。セコムがセキュリティ事業で培った緊急時対応の経験とノウハウを凝縮した安否確認サービス。すべてを機械任せにはせず、人間の判断力・機動力・処置力を組み合わせた24時間365日体制のオペレーションが特徴。セコムあんしん情報センターが地震情報だけでなく、様々な情報源から災害情報を入手し、管理者に代わって従業員への安否確認メールを代行送信。送信手段は、メール・専用アプリのプッシュ通知・LINE連携の3つ。
管理者用・社員用画面を日本語と英語の切り替え表示ができるほか、英語の運用マニュアルもあり。外資系企業や大使館などの導入実績も豊富。

(出所:オクレンジャー公式Webサイト)
災害に強い安定したインフラに強みをもつ安否確認サービス。国内外3カ所にサーバーを設置し、国内で大規模災害が発生した場合はサーバーを海外に切り替えられる。月間稼働率が99.9%を下回った場合に利用料を減額する品質保証制度も心強い。メールアドレス・電話番号を一切使用せずに連絡網を構築できるスマホアプリとして特許を取得している。
従業員一人あたりが登録できる端末台数やメールアドレス数に制限がないのも強み。業務用と私用の両方で登録できるため、どちらか一方の回線が不通になっても連絡がとれる可能性が高まる。厚生労働省推奨のストレスチェックや、Bluetooth連携したアルコールチェックなど、平時の利用に役立つ機能も。

(出所:ALSOK安否確認サービス公式Webサイト)
災害情報と連動して安否確認連絡を自動配信できる安否確認サービス。国内の複数拠点にサーバーを設置することで災害時の稼働率を確保。震災でも安定稼働した実績あり。安否確認連絡はメールのほか、専用アプリでのプッシュ通知にも対応。
GPS機能や写真を用いた報告や社内掲示板を用いたやりとり、家族を含めた安否確認など基本機能も充実。オプションで英語表示にも対応している。
“安否確認システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)

(出所:ANPIC(アンピック)公式Webサイト)
南海トラフ地震を想定して、静岡大学・静岡県立大学により産学連携で共同開発された安否確認システム。国公立大学の間では40%以上のシェアを誇る。
50名までなら月額5,130円から利用可能。安価ながらも高機能で、メール・アプリに加えて、LINE通知も追加料金なしで利用可能。普段使用しているLINE上で通知・回答を行えるため安否確認やアンケートの回答率向上が期待できる。そのほか、リトライ、集計内容のグラフ化、ユーザー情報の一括登録、既存の人事システムなどとのデータ連携、手動メール機能やアンケート機能も標準装備。

(出所:安否確認bot for LINE WORKS公式Webサイト)
個人アカウントを含むすべてのLINEシリーズで安否確認メッセージを受信できるソリューション。従業員の回答方法は、スマホに最適化されたLINE WORKSのチャットbotから安否確認の選択肢ボタンをタップするだけ。ログイン不要で簡単に回答できるため、管理者はメールアドレスやID、パスワードなどの名簿管理をする必要もなし。管理業務の負担を軽減できる。
更に、LINE WORKSを利用していない従業員も、「ゲスト従業員」としてメールで安否確認を受け取ることが可能。配信されるメール本文内にあるURLにアクセスするだけで回答できる。また、ゲスト従業員はLINE WORKS従業員と同様に、入社・退職に伴う個別追加・削除、CSVによる一括追加・削除に対応。すべての従業員をもれなく管理できる。

(出所:バンソウ緊急SMS公式Webサイト)
SMS(ショートメッセージ)を利用した安否確認サービス。地震などの災害が発生したら、SMSで安否確認メッセージを自動送信。従業員はSMSに記されたURLからWebフォームにアクセスして回答。結果は自動で集計され、管理者はWeb画面から送信数・開封数・回答数などの状況を簡単に把握できる。
SMSはスマホにデフォルトで登録されているため、わざわざアプリをダウンロードする手間がかからない。迷惑メールなどに紛れる可能性のあるメールと異なり、開封封率が高いのも特徴。
“安否確認システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)

(出所:ANPiS公式Webサイト)
気象庁の災害情報との連動による自動送信に対応した安否確認システム。災害情報は地震・津波・大雨・洪水・大雪などに対応。回答の自動集計、未回答者への自動リトライ、アンケートなど基本機能が充実。手動送信を使えば家族への安否確認も行える。組織階層は4階層まで対応していたり、部署横断でのグループ設定にも対応していたりするため、大企業で部署が多い場合でも管理しやすい。
料金は初期費用無料で、利用人数に応じた従量制。最小プランなら月額6,000円から利用可能(50名まで)。人数が増えるほど1名あたりの単価は下がるため大規模組織にもおすすめ。

(出所:クロスゼロ公式Webサイト)
緊急時の安否確認だけでなく、被害を最小限に食い止めるための様々な機能を備えた総合防災アプリ。安否確認に関しては、自動配信・集計のほか、掲示板・チャット・ファイル共有などの機能が一通り揃っている。特徴的なのは、近隣のハザードマップや避難場所を作成できたり、どのような備蓄品があると良いかがリスト化されていたり、日頃から災害に対する意識付けがしやすいようになっているところ。
料金は年契約で、最小のベーシックプランなら年額60,000円(50名まで)。一通りの機能が揃ったBCP対策プランでも年額90,000円(50名まで)で利用可能。初期費用がかからないのもおポイント。

(出所:らくらく連絡網公式Webサイト)
700万人が利用する無料メーリングリスト。連絡先を知らなくても、連絡手段が異なっても、共通のプラットフォームとしてやりとりできる点から、通常は団体や学校等でのイベント活動で用いられているが、安否確認にも利用可能。
「安否確認」を選んで送信すれば、宛先やタイトルも本文を入力せずとも、メーリングリストのメンバー全員に送信可能。送信者は一画面上でそれに対する既読・未読、コメントを確認できる。基本無料だが、メルマガ配信や広告表示をさせない有料版への移行も可能。

(出所:e安否公式Webサイト)
20名までなら無料で利用できる安否確認システム(一部機能制限あり)。GPS機能を標準搭載しており、安否確認の回答と同時に位置情報も取得。社員へ避難経路の指示や待機場所の指示なども効率よく行える。
特徴的なのは支部や部署などを階層として、社員を「組織図」で視覚的に管理できるところ。組織・部署・部門ごとに責任者を立てて柔軟に操作・閲覧権限を設定することもできるため、組織の変更に合わせて運用方法も変更しやすい。
安否確認システムを利用すれば、地震などの災害発生が起こった際、管理者に負担をかけず、スムーズに従業員の安否確認をとることができます。「個々の状況を速やかに把握し、それに合わせた指示を出せる」という点が評価され、東日本大震災以降、多くのシステムが登場するようになりました。
自社に合った安否確認システムを選ぶ際には、まずは以下の3タイプからどれにあてはまりそうか検討してみましょう。
ある程度タイプを絞れたら、「自動通報機能」「連絡手段」「動作実績」「登録・認証方法」「家族の安否確認」「多言語対応」など、紹介したポイントに沿って比較検討してみるとスムーズです。「どうしてもコストがかけられない」という場合は、無料で利用できるサービスを利用して「どんなものか」試してみるのも一手です。
安否確認システムは万一のリスクのための予算投下のため、通常の稟議よりも難しくなりがちですが、企業の将来のための重要な投資であることは間違いありません。必要な機能と、かけられる予算を見定めながら、自社にとってバランスのよいものを選ぶようにしましょう。
安否確認システムをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。
“安否確認システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)
選び方をもっと詳しく知りたいという場合は、こちらのガイドブックもぜひ参考にしてください。
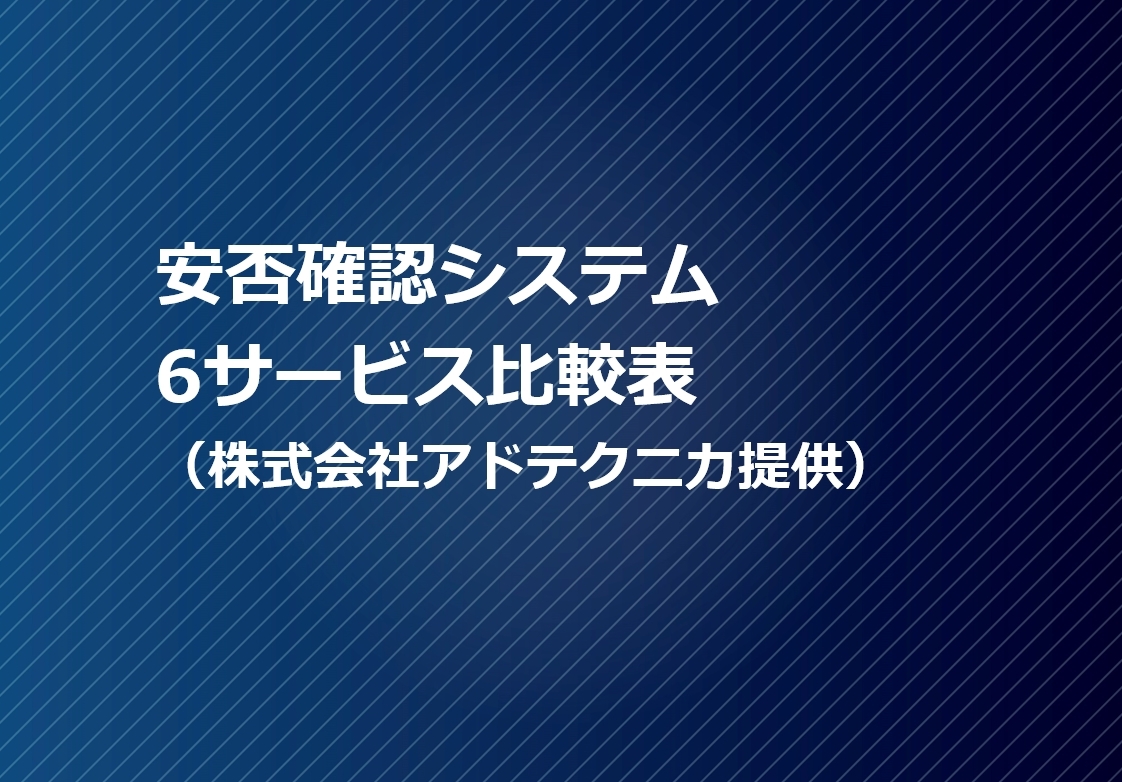
安否確認システム 6サービス比較表(株式会社アドテクニカ提供)
株式会社アドテクニカ
「ASPIC IoT・AI・クラウドアワード」「グッドデザイン賞」受賞。3.11でも問題なく稼働した実績を持ち、上場企業をはじめ1,300社以上で導入されている...
インフォコム株式会社
2拠点同時稼働で大災害発生時でも安定したサービス提供を実現する安否確認システム。危機管理ポータルサービスとも連携し、情報共有をサポート。事業継続を支えます。...
株式会社ジェネストリーム
すべてのLINEシリーズで従業員の安否確認を自動で実施するシステム。回答はログインやWebへのアクセス不要。LINE WORKS内のチャットbotで回答も簡単。...
関西電力株式会社
必要な機能に絞ったシンプルな設計により、月額6,600円(税込)からの低価格で導入できる安否確認システム。コストを抑えつつ、BCP対策をしっかり行いたい企業にお...
<重要なお知らせ> サイトリニューアルに伴い、初回ログインにはパスワードの再設定が必要です。
アスピックご利用のメールアドレスを入力ください。
パスワード再発行手続きのメールをお送りします。
パスワード再設定依頼の自動メールを送信しました。
メール文のURLより、パスワード再登録のお手続きをお願いします。
ご入力いただいたメールアドレスに誤りがあった場合がございます。
お手数おかけしますが、再度ご入力をお試しください。
ご登録いただいているメールアドレスにダウンロードURLをお送りしています。ご確認ください。
サービスの導入検討状況を教えて下さい。
本資料に含まれる企業(社)よりご案内を差し上げる場合があります。