「経費精算システムは費用をかけてまで導入すべきなのか」とお悩みの経理担当や総務担当の方へ。そもそも経費精算システムとは何か、どのような機能があるのか。導入のメリット・デメリット、システムの選び方まで、わかりやすく解説します。
“経費精算システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)
経費精算システムとは、経費精算を行う上で必要な申請、チェック、承認などの業務を効率的に行うためのシステムです。
紙やExcelによる従来型の経費精算の場合、申請・承認をする上で様々な課題が生じます。
たとえば、交通費の申請では金額の間違いが起こりがちなため、経理担当者は全件確認を強いられることに。また、仕訳に関しても申請ごとに行う必要があり、会計システムなどに転記するのを考慮すると、途方もない時間と手間がかかってしまいます。
経費精算システムなら、交通費は従業員が駅名や交通手段を入力するだけで自動計算されるため、ミスを大幅に削減可能。また、申請時に内訳を選択するだけで、承認時に自動で仕訳されるため、格段に作業効率が上がります。
更に、会計システムと連動させることで、データの取り込みがスムーズに行えることなども大きなメリットです。
| 領収書の読み取り・自動入力 | 精算したい領収書を画像にして読み込ませると、項目や金額を自動で拾い上げてくれる。自分で入力する手間が省ける。 |
|---|---|
| 交通費の自動計算 | 乗換案内ソフトと連携することで、目的地を入力するだけで交通費を自動計算して申請してくれる。 |
| ICカードとの自動連携 | 交通系ICカードと連携することで、乗り換え履歴を読み取って、自動で申請を行える。 |
| 振込データの自動作成 | 振込データ(FBデータ)を自動作成。オンラインで振込処理できる。 |
| 自動仕訳機能 | 勘定科目や税区分などを選択するだけで、会計上で自動仕訳される。 |
| 外部ツールとの連携機能 | 会計システムや給与システム、勤怠管理など、既存のツールと連携できる。データの一元管理が可能になる。 |
経費精算システムをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。
“経費精算システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)
経費精算システムの導入メリットは、以下の3つに大別できます。
経費精算システムを導入し、システム上で乗車区間を入れると、実際に乗車したルートを選択したうえで料金が自動で入力されます。わざわざインターネットの路線検索サービスで乗車区間を入れて検索し、一つずつ運賃を調べる必要がなくなります。手間が軽減されるだけでなく、調べ間違いをなくし、不正防止にもつながるため非常に便利な機能です。
特に、定期券を利用している場合に効果を発揮します。ほとんどの会社では定期券が適用された後の運賃で申請することになっていて、この計算に手間を感じている人も多いでしょう。経費精算システムでは、あらかじめ定期券区間を設定すれば自動で運賃が計算されるので、負担がかなり軽減されます。
連携されたSuica、PASMOなどの交通系ICカードを読み込んで入力するサービスもあります。
領収書・レシートを写真撮影し、OCRで文字認識して自動入力するサービスを利用すれば、入力の手間がかなり削減されます。ただし、自動入力される項目は日付、金額、支払先、といったものなので、それ以外の品目や「〇〇社△△氏との打ち合わせ」といった特記事項は手入力する必要があります。中には、手書きの領収書をオペレーターが代行入力するサービスも。
今までは、伝票入力したり領収書を糊で貼ったり、といった作業が億劫で、ついつい月末まで溜め込んでしまうというケースも多かったかもしれません。また、オフィスでしかできない作業のため、外出の多い営業担当者などは後回しにしがち。クラウド型の経費精算システムを導入すれば、外出先や移動中でも簡単にスマホで写真撮影・申請が可能となり、スピードアップを実感できるでしょう。
写真撮影しての申請や、ICカード連携、スマホでの申請など、申請者にとっては入力しやすい環境に。手順が楽なだけでなく、煩雑な入力作業から解放され、心理面でもハードルが下がります。入力の遅れや、締め切りギリギリにまとめて提出するといったこともなくなるでしょう。
申請者側のメリットで述べたことにつながりますが、確認する経理側としても交通費精算ではあらゆるチェックが楽になります。特に、申請区間が定期券の区間でないかのチェックは一つひとつ調べる必要があったのが、経費精算システム上で定期券の利用区間を設定しておくことで、自動計算されるようになり、手間が大幅に削減されます。
会計ソフトと連携しているシステムを利用すれば、改めて入力の手間がなく、非常に便利です。自動で仕訳され、勘定科目を決める必要もなくなります。
経費精算システムの利用により、振込データの自動作成でインターネットバンキングに取り込むだけになり、煩雑な振込作業からも解放されます。
申請内容に不備がある場合は、システム上でコメントを書いて申請を差し戻すことでスムーズに対応できます。紙ベースの場合は伝票を持って申請者へ指摘箇所を伝えに行き、また承認を受ける、という手間がかかっていましたが、スピードアップが見込まれます。
また、万が一金額に誤入力があり、経理側で修正した際は、修正して承認した旨を伝えればよいので、わざわざ申請者へ連絡しに行く必要もなくなります。
そもそも、経費精算システムを利用することで、金額の入力ミスというものが大幅に減るはずです。交通費は自動計算され、領収書から自動取り込み。システムによっては、規定違反の申請が自動で承認エラーになるように設定できますので、間違った申請が経理まで上がってくる割合は、ぐっと減るでしょう。
入力未完了者が抽出できるため、誰がまだ申請していないかが分かり、すぐに催促できるようになります。申請の承認はワークフローで行われるので、承認者が出張に行っていても対応できますし、滞っている場合はどこで止まっているかすぐにわかります。
「出張中の上長のデスクにある書類の束から引っ張り出して、権限委譲されている部の上長にハンコをもらいに行く」などという面倒なこともありません。
電子帳簿保存法に対応したシステムであれば、領収書を電子保存できるようになります。紙管理から解放されると、膨大な紙ファイルの保管場所の確保が不要に。新たな保管時や7年間保管後の廃棄時、ちょっとした調べものの際に保管場所へ足を運ぶ必要もなくなり、その時間を別の業務に充てることができます。
経理は他部署に比べて多くの保存書類に囲まれがちですが、その分、ペーパーレスによる効果は大きいのです。
経費精算システムのワークフロー機能を活用することで、トラブルを未然に防ぐこともできます。
たとえば、社内ルールで物品購入や出張に対して事前稟議が必要となっている場合、ワークフローを利用して事前申請を受け付けるようにすれば、誰の承認で買ったのか、誰の承認で出張に行ったのかがわからない、といった事態も回避できます。
一般的に、経費精算システム導入における大きなデメリットはありません。ただし、注意点はいくつかありますので、ご説明します。
メリットの項で、申請者も経理サイドも手間を削減できると紹介しましたが、必ずしもそうではないケースもあります。
たとえば、交際費申請として飲食代を精算する場合は、どの目的で・誰と・どこで飲食したのかなどを、一通り申請しなくてはなりません。OCRで自動入力される項目も限られていますから、手入力が必要です。「期待したほど手間が減っていない」と思うことや、「どうせ手入力をするのなら、わざわざシステムを導入しなくてよい」と思うこともあるかもしれません。
また、申請画面に行きつくまでが複雑だったり、自社には不要な機能が多かったりすると、どうしても面倒と思われてしまいます。よって、画面の操作性は非常に重要です。使い方がわかりにくくて、経理やIT部門に質問が殺到することは絶対に避けるべき。直感的に操作できる、使いやすいシステムを選ぶことが重要です。
経費精算システムは利益を生まないシステムですが、経営陣も日々利用するため、比較的稟議の場で説明しやすいシステムかもしれません。とはいえ、決して安価なシステムではないので、他社事例をもとに「月初の経理担当者の残業時間が〇〇時間減らせる」などの費用対効果の説明は必要でしょう。
この点はシステム提供会社が知見や経験、成功事例を多く持っていますので、費用対効果の出し方については相談してみてもよいでしょう。
当然のことながら、会計ソフトとの連携を考える場合、自社のソフトとの連携ができるシステムを選ばなくてはなりません。システムと連携できるとはいっても、データの範囲はどこまでで、どのような状態で渡されるのかなど、細かく詰めていくと、希望通りに連携できないこともありえます。
連携できない部分を別プログラムや手作業で埋めていくとますます大変になってしまうので、IT部門を巻き込んだ詳細な仕様詰めが必要です。
他にも、セキュリティ面での不安要素や、社内での浸透方法や社内で変化を嫌がる人への対応、本当に必要な機能を備えているか、といった点も考慮しておきましょう。
経費精算システムの選び方を、導入する目的別にご紹介します。
入力の際に手間やミスが軽減されるよう、領収書のスキャン機能やICカード連携対応などに強いものがおすすめです。従業員の入力がスムーズになれば、申請を受理する側の経理にとっても時間や正確性の面でメリットがあります。
自社で利用している会計ソフトとの連携面をポイントに選ぶのがよいでしょう。中には、会計ソフトを提供している企業が展開している経費精算システムもあります。
出張や交際費は一部の人のみで、ほとんどの人は交通費のみ、といった企業であれば、多機能タイプの経費精算システムでは使いにくい可能性があります。
交通費精算に特化したサービスは多いため、交通費精算が主であれば、経路計算や定期券対応などの機能が充実しているものを選ぶとよいでしょう。経路探索サービスを運営している企業が提供している経費精算システムもがおすすめです。
中には、交通費と勤怠管理が一体化したシステムも。毎日の出退勤時に交通系ICカードをスマホやカードリーダーにタッチするだけで日々の交通費精算と、出退勤の記録がされる、というシンプルな機能のサービスもあります。
たとえば、外出する人が多く、PCよりは会社貸与のスマホで業務することが多い場合、スマホで申請から承認まで完結できるタイプがよいでしょう。外回りが多く、なかなか会社のデスクで申請作業に取り組めない、ということもありません。締め切りギリギリにまとめて提出されることが減り、受理する経理側の作業も大幅に改善されるはずです。
海外拠点でも使う場合や外国人の多い企業の場合は、多言語対応はポイント。そのほか、海外出張の多い人には、指定した日の為替レートへの自動変換機能もとても便利です。
また、母体としてグループウェアやワークフロー、勤怠管理システム、家計簿アプリ、などを運営している企業が展開する経費精算システムもあります。すでにそのサービスを利用しているなら、操作性の面ですぐに慣れるメリットがあります。仮に利用していなくても、それと一緒に導入することも判断材料の一つとなるでしょう。
経費精算システムについて、より詳しい選び方や検討ポイントを知りたい方は、「経費精算システム比較15選!機能やタイプ別(図解)の選び方を紹介」も参照ください。
選び方を踏まえて、おすすめの経費精算システムをご紹介します。
“経費精算システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)

(出所:楽楽精算公式Webサイト)
クラウド型の経費精算のため、スキマ時間を利用した経費精算が可能。たとえば、AI機能搭載の領収書読み取り機能を利用すれば、従来の申請に必要だったデータ手入力を省ける。経費精算規定に沿わない申請がされた場合には警告が出るように設定することも可能。差し戻しの手間が省けるだけでなく、申請ミスを防ぐための内部統制強化にもつながる。汎用ワークフロー機能も充実。申請フォーマットのレイアウトや項目を自由に組み合わせられ、会社ごとに異なる書式や承認フローをシステム上で再現できる。その他、自動仕訳・会計システムに連携したデータ出力機能、全国銀行協会フォーマットで振込データ(FBデータ)の作成、各種振込代行サービスともデータ連携が可能なため、経理担当者の作業負担も軽減できる。

(出所:Concur Expense公式Webサイト)
国内では1,620社以上、世界では8,000万人以上に利用されている経費精算システム。申請から承認までスマホアプリで行え、外部サービスとの連携による自動取り込みにも強みをもつため、経費精算時間を83%削減すると定評あり。
また、経費精算の範囲は、交通費・一般経費だけでなく、出張の予約・申請はConcur Travelで対応できる。
コーポレートカード、スマホ決済アプリ、交通系ICカード、路線検索連動による支払い情報の自動取り込み、スマホアプリを用いた領収書撮影によるOCR読み取り等のほか、タクシーアプリ、宿泊予約サイト、名刺情報管理サービスなどの外部サービスとの連携による支払い情報の自動取り込みにも対応しており、手間を大幅に削減。
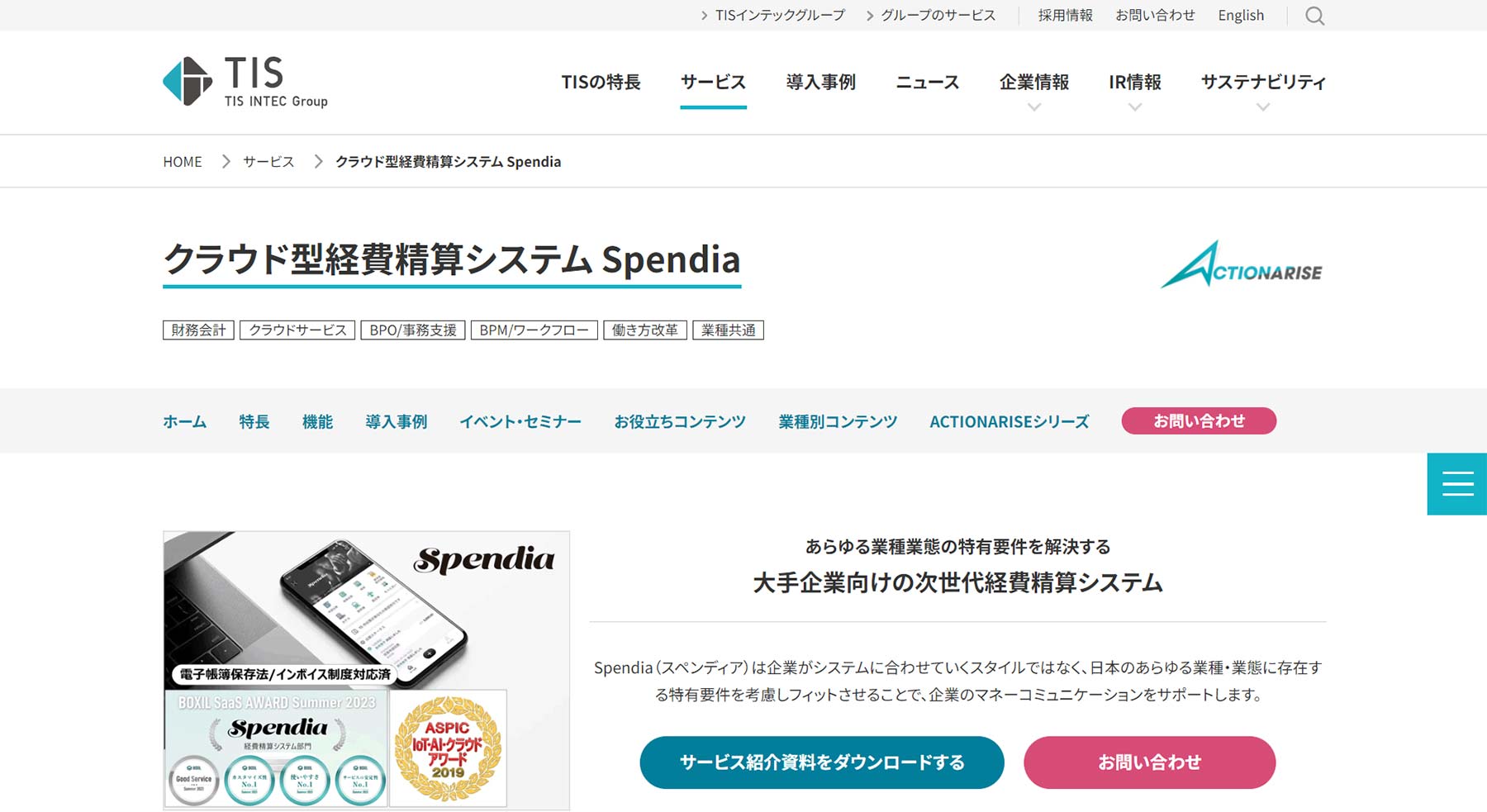
(出所:Spendia公式Webサイト)
従業員300名以上の中規模・大企業向けの経費計算システム。スマホでは専用アプリで経費申請から承認まで行える。請求書AI-OCR自動入力やGPS移動距離精算、経路検索・定期控除機能など、様々な入力サポート機能で入力を効率化できる。大規模組織で必要な複雑な旅費規程などの各種規程対応は、プログラミングなしでドラッグ&ドロップ操作で設定に反映できる仕組み。そのほか、航空券やホテルなどの予約ができる予約・手配機能にも対応。経理業務全般を効率化させるためのRPAとの連携も強み。

(出所:WiMS/SaaS経費精算システム公式Webサイト)
クラウド型の各種業務システムWiMS/SaaSシリーズの中の経費精算システム。グループ会社をまたいだ経費承認や会社間取引、親会社代行支払い等が可能。操作性の高い入力画面と科目に紐づいた入力支援機能を実装。交通費、出張費、立替の精算といった一連の申請・承認・精算ワークフローにおいて、手間のかかる経費精算業務の負担を軽減。ジョルダン乗換案内と連動しており、使用経路を選択するだけで自動入力される。会計システム連携、FBデータ作成、ワークフロー承認など、経理業務をワンストップで行うことで効率化に貢献。利用中の会計システムに合わせて仕訳データを柔軟に出力し、自由度の高い連携を実現可能。

(出所:TOKIUM経費精算公式Webサイト)
シリーズ累計導入実績は2,500社以上、テレワークやペーパーレス化の実現に役立つ経費精算システム。モバイルSuica等の自動連携をはじめ、経理に一枚も領収書が回ることなく、入力後の紙類全ての管理まで任せられるサービス。領収書・レシートをスマホで撮影するだけで、データベースと目視チェックで、99%以上の高精度でデータ化。そして領収書を撮影した後、専用ポストに入れることだけで、領収書を回収して、経費申請に対応する領収書原本がちゃんと投函されているかの全数点検、保管といったすべての工程を代⾏してくれる。利用ID数に上限がないため、全従業員にIDを付与することができる点も特徴。

(出所:チムスピ経費公式Webサイト)
経費精算以外の機能も併せ持ち、これ一つでバックオフィス業務の効率化が図れる点が特徴の経費精算システム。導入実績は2,000社以上。業務システムの刷新や、テレワークのための一斉導入を検討している企業に選択肢。経費精算のほか、勤怠管理、工数管理、電子稟議などの機能も併せ持つ。既存のERPシステムの上にアドオンすることで利用でき、勤怠打刻と兼用することでの精算処理の効率化や経費精算の申請から承認までのワークフローの一体化など実現できる。
経費精算の機能も充実しており、乗換案内連携、クレジットカード利用明細取り込み、領収書のOCR読み取り、ワークフローによる承認、外部データ出力など可能。モバイルアプリも対応している。

(出所:ジンジャー経費公式Webサイト)
ジンジャーシリーズの経費精算システムで、シリーズの導入実績は中小企業から大企業まで幅広く18,000社超。シリーズの他システムを一人あたり数百円で組み合わせて導入できるため、勤怠管理や給与計算、人事管理などを一つのプラットフォームでデータ連携して利用できる点が特徴。経費精算とあわせて人事関連業務のシステム化を検討する企業におすすめ。経費精算、交通費、交際費、支払いの申請に対応。自社の会計ソフトに合わせた仕訳データ出力や、FBデータの自動作成等で、経理担当者の手間を大幅に削減。「駅すぱあと」乗換案内との連携、定期区間の控除、スマホからのレシート添付など、経費精算に役立つ一通りの機能が充実。従業員画面だけでなく、管理者画面もスマホアプリに対応している。

(出所:MAJOR FLOW 経費精算/支払依頼公式Webサイト)
社内規則に則った複雑な申請・承認フローをすべてシステム化したいときに選択肢となる経費精算システム。ワークフローMAJOR FLOWシリーズのシステムのため、他の経費精算システムではカバーしきれない複雑な条件分岐や代理申請、引き上げ承認などに対応している。入力の効率化を実現する機能は、経路検索ソフト連携、交通系ICカード連携、クレジットカード連携等、一通り揃っている。また、自動仕訳、各種会計システム連携、各種帳票のExcel出力、電子帳簿保存法対応、最大5言語までの多言語設定など、管理部門の効率化が期待できる機能も充実。スマホ・タブレット対応。同一テナント内のグループ会社など、複数の企業での運用、企業を跨いだフローも実現可能。

(出所:経費BANK公式Webサイト)
1ID300円から使えるスマホ対応の交通費・経費精算システム。コーポレートカード連携により、カード明細をシステムに自動連携することが可能で、入力の手間やミスを防いで、企業のキャッシュレス化を推進できる。交通系ICカード連携でき、定期区間の控除もできる「駅すぱあと」を標準搭載。部門や役職に合わせた承認ルート設定や、支払・仕訳データ出力にも対応しており、申請書のカスタマイズも簡単にできるなど、低価格ながら機能が揃っている。英語表示にも対応。電子帳簿保存法の「スキャナ保存」と「電子取引」のデータ保存に対応したオプションサービスを用意しており、タイムスタンプ機能や検索・一括検証機能を備え、スマホの読取りにも対応。

(出所:ハーモス経費公式Webサイト)
中小~大企業、大学、金融機関などへ、20年以上の導入実績。電子帳簿保存法対応。クラウド型とオンプレミス型があり。領収書AI-OCR機能で、外出先で受け取った領収書・レシートをその場で読み取り、自動入力できる。交通系ICカード読込機能では、ICカードの登録の制限、交通履歴のみの表示、二重取込防止、定期区間控除などチェック業務を軽減する機能が豊富。Amazonビジネスと自動連携可能で、商品の購買プロセスを効率化できる。

(出所:マネーフォワード クラウド経費公式Webサイト)
会計ソフト等を展開するマネーフォワード社が提供する経費精算システム。金融機関の口座やクレジットカード、ECサイトや航空会社サイト等と連携して登録すると、自動連携されるなど、連携の幅に強み。APIを利用して会計システムとの接続ができ、従業員、部署、プロジェクトなどの各マスタとの同期や仕訳データの連携が可能。レシートのOCR読み取り機能だけでなく、オペレーターの代行入力サービスもあり。プランにより、電子帳簿保存法対応。

(出所:バクラク経費精算公式Webサイト)
領収書読み取りに特化したAI-OCR搭載の経費精算システム。申請者は領収書をまとめてアップロードするだけで、領収書を自動でデータ化。日付や金額などの情報を手入力する手間を大幅に削減。経理担当者は、申請内容の確認や入力ミスのチェックにかかる時間を削減できる。電子帳簿保存法・インボイス制度にも対応。
二重申請や予算超過を自動検知するアラート機能も搭載しており、不正を防止。更に、スマホアプリを利用することで、場所を選ばずに経費申請や承認作業が可能に。オプションで、経費精算だけでなく、稟議・承認・支払まで一気通貫のシームレスな内部統制を実現できる。

(出所:MOT経費精算公式Webサイト)
紙やExcel管理からシステム化への切り替えに強みを持つ経費精算システム。導入企業の中には80%削減した事例も。交通ICカード連携可。PCでもスマホでも承認・申請完了。クラウド文書管理システムのMOT文書管理と連携すれば、電子帳簿保存法やインボイスにも対応。スマホアプリなどは今後対応予定だが、1IDあたり月額199円〜と安価で始めやすいのも魅力。リモートアクセス「V-Warp」の利用で、遠隔地から社内のPCへ安全にアクセスでき、在宅勤務・テレワークにも便利。
経費精算システムとは、経費精算を行う上で必要な申請、チェック、承認などの業務を効率的に行うためのシステムです。経費精算システムの導入メリットは、以下の3つです。
(1)申請者の入力の手間削減
(2)管理系スタッフ(経理)の手間削減
(3)内部統制の強化
この記事を読んで経費精算システムが気になった方は、まず直近の自分の経費精算業務がシステム導入によってどのように変わり、その結果当初の目的が実現できそうかを考えてみましょう。そのうえで、ご紹介したおすすめの経費精算システムを検討してみてください。
経費精算システムをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。
“経費精算システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)
経費精算システムの詳しい選び方は、こちらの選び方ガイドや機能比較表をご覧ください。
経費精算システムの選び方ガイド(比較表付き)
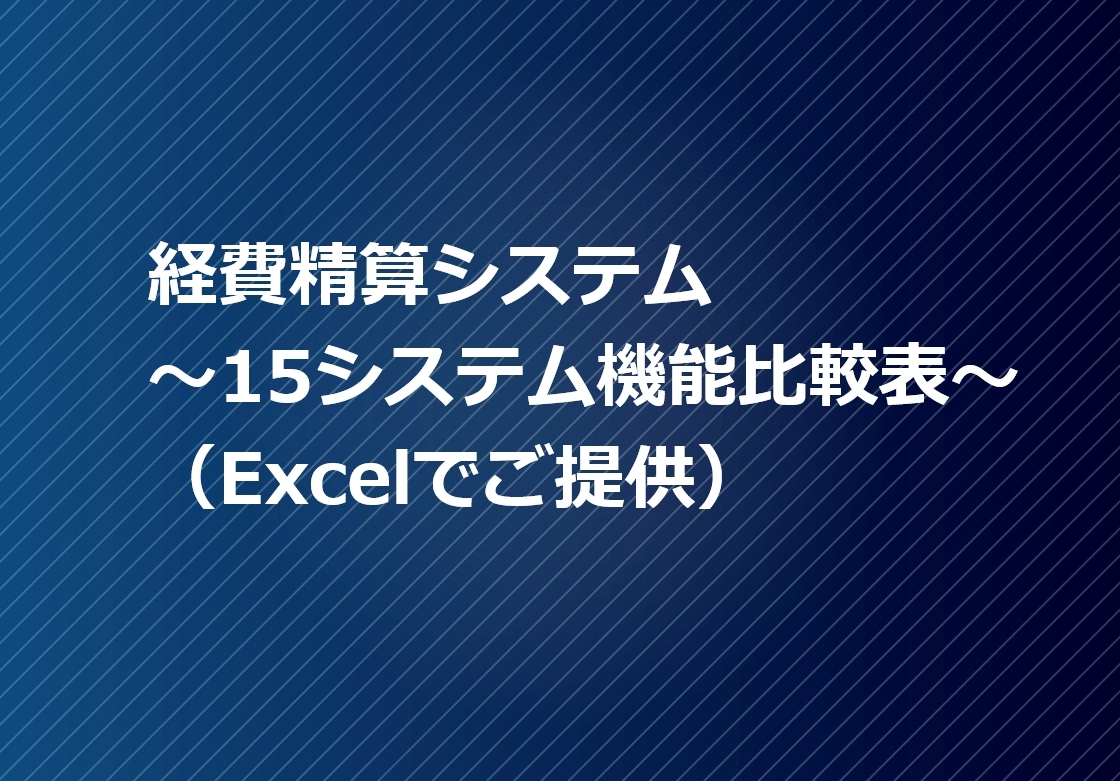
経費精算システム 機能比較表(15システム)
株式会社ラクス
18,000社以上が導入する国内累計導入社数実績NO.1の経費精算システム。経費の申請・承認・経理処理をクラウド上で完結することで、申請者や経理担当者の作業効率...
株式会社コンカー
国内売上8年連続 No. 1。国内外で最も使われている経費精算・管理クラウド。経費精算時間を83%削減。顧客満足度95%。平均投資回収期間はわずか7.3カ月。...
TIS株式会社
日本企業特有の制度や商習慣に合わせて開発したエンタープライズ企業向け経費精算クラウドサービスです。SI力や最新テクノロジーを活かして大企業ならではの課題を解決し...
株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー
WiMS/SaaS経費精算システムは、従業員の経費の申請や交通費の精算など、一連の申請・承認・精算ワークフローを行う、クラウド型経費精算システムです。...
株式会社TOKIUM
経費精算作業の削減時間No.1。経理担当者の作業時間を最大90%削減すると同時に、経理部門のペーパーレス化・テレワークを実現するクラウド経費精算システムです。...
パナソニック ネットソリューションズ株式会社
申請から支払い処理までを一元管理できるWeb経費精算システム。Webブラウザで承認されたデータの計上処理や仮払・戻入金管理や支払業務が行えます。...
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
1ID300円から使えるスマホ対応の交通費・経費精算システム。クラウド型でいつでもどこでも承認・申請が可能。電帳法にも対応しており、経理処理からシステム管理まで...
株式会社マネーフォワード
経費精算の自動化で経費にかかる時間を1/10にできるクラウド型経費精算システム。カード明細や交通系ICカードの自動読取、レシート入力の自動化などで徹底的に手入力...
<重要なお知らせ> サイトリニューアルに伴い、初回ログインにはパスワードの再設定が必要です。
アスピックご利用のメールアドレスを入力ください。
パスワード再発行手続きのメールをお送りします。
パスワード再設定依頼の自動メールを送信しました。
メール文のURLより、パスワード再登録のお手続きをお願いします。
ご入力いただいたメールアドレスに誤りがあった場合がございます。
お手数おかけしますが、再度ご入力をお試しください。
ご登録いただいているメールアドレスにダウンロードURLをお送りしています。ご確認ください。
サービスの導入検討状況を教えて下さい。
本資料に含まれる企業(社)よりご案内を差し上げる場合があります。